第6章:ホームページを作る際に考えるべきポイント (2)デザインや構成の重要性
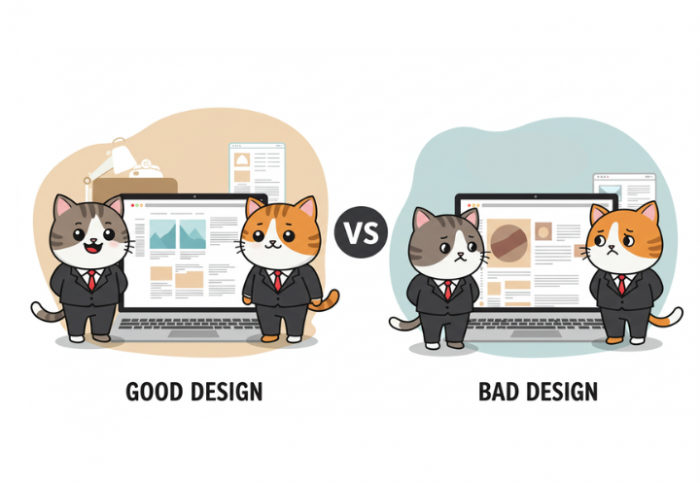
前回は、ホームページ制作における目的設定の重要性について解説しました。目的が明確になったら、次に考えるべきなのがデザインと構成です。多くの人が軽視しがちですが、実はこの「見た目」と「情報の整理」が、ホームページの成功を大きく左右します。
なぜなら、どれだけ素晴らしいコンテンツがあっても、デザインが古臭かったり、情報が整理されていなかったりすると、訪問者はその価値に気づく前にページを離れてしまうからです。今回は、効果的なデザインと構成について詳しく見ていきましょう。
わずか数秒で決まる「第一印象」の重要性
3秒ルールとその対策
ホームページを訪れた人は、わずか3秒程度でそのサイトを見続けるかどうかを判断すると言われています。この短い時間で「信頼できそう」「欲しい情報がありそう」「見やすい」と感じてもらえなければ、どれだけ時間をかけて作ったコンテンツも読まれることはありません。
この3秒で好印象を与えるには、パッと見ただけで「何の会社なのか」「どんなサービスを提供しているのか」「信頼できるのか」が伝わるデザインが必要です。ごちゃごちゃした情報を詰め込むのではなく、重要なメッセージを明確に、そして魅力的に伝える工夫が求められます。
古いデザインが与える悪影響
古臭いデザインのホームページは、会社全体のイメージにも悪影響を与えます。「この会社は時代についていけていないのでは?」「サービスの質も古いのかもしれない」といった不安を与えてしまう可能性があります。
特に競合他社が現代的で洗練されたホームページを持っている場合、比較されることで大きなハンディキャップとなります。デザインへの投資は、単なる見た目の問題ではなく、ビジネスの競争力に直結する重要な要素なのです。
業種・目的に応じたデザイン戦略
士業・専門職の場合:信頼性と専門性を重視
法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社などの士業・専門職では、何よりも信頼性と専門性を感じさせるデザインが重要です。落ち着いた色合い、整理された情報、清潔感のあるレイアウトが求められます。
過度に派手なデザインや奇抜な演出は逆効果になることがあります。むしろ、シンプルで上品なデザインを通じて「この専門家なら安心して相談できる」という印象を与えることが大切です。資格情報、実績、専門分野などを分かりやすく整理して掲載することも重要なポイントです。
クリエイティブ系企業の場合:独創性と感性をアピール
デザイン会社、広告代理店、映像制作会社などのクリエイティブ系企業では、そのホームページ自体が「作品」としての役割も果たします。独創性、感性、技術力を直接的にアピールできる絶好の機会です。
他社とは一線を画する個性的なデザイン、最新のウェブ技術の活用、印象に残るビジュアル表現などを通じて、自社の創造力とスキルの高さを証明することができます。ただし、個性を追求しすぎて使いにくくなってしまっては本末転倒なので、バランスが重要です。
飲食店・小売店の場合:商品の魅力と親しみやすさ
飲食店や小売店では、商品の魅力を最大限に伝える写真の活用が極めて重要です。美味しそうな料理の写真、魅力的な商品画像、お店の雰囲気が伝わる内装写真などを効果的に配置することで、「行ってみたい」「買ってみたい」という気持ちを喚起できます。
また、親しみやすさを感じさせるデザインも大切です。堅苦しすぎず、でもチープに見えない絶妙なバランスを保ちながら、お客様に「気軽に利用できる」という安心感を与える必要があります。
BtoB企業の場合:信頼性と実績を重視
BtoB企業では、取引先や関係者が「安心して取引できる会社か」を判断するためにホームページを訪れることが多くあります。そのため、会社の規模感、実績、取引先企業、財務の安定性などが伝わるデザインと構成が重要になります。
代表者のメッセージ、会社概要、事業実績、取引先企業一覧などを分かりやすく整理し、「この会社となら安心して長期的な取引ができる」という印象を与えることが求められます。
情報の整理と構成の基本原則
メニュー構成の考え方
ホームページのメニュー構成は、訪問者が迷わずに目的の情報にたどり着けるかを左右する重要な要素です。一目見ただけで「どこに何があるか」がわかるような、分かりやすい名称と論理的な配置を心がけましょう。
会社の組織図や事業部門に合わせてメニューを作るのではなく、訪問者の視点に立って「何を知りたがっているか」を考えることが大切です。例えば、「第一事業部」「第二事業部」といった内部の名称ではなく、「個人向けサービス」「法人向けサービス」など、外部の人にも分かりやすい名称を使用します。
情報の優先順位づけ
限られた画面の中で、すべての情報を同じ重要度で扱うことはできません。訪問者にとって最も重要な情報、会社として最もアピールしたい情報を明確にし、それらを目立つ位置に配置する必要があります。
重要度の高い情報ほど、ページの上部や中央など、目につきやすい場所に配置します。逆に、詳細な会社情報や規約などの補助的な情報は、必要な人だけがアクセスできる場所に配置することで、全体的にすっきりとした印象を保つことができます。
視覚的な導線設計
訪問者がホームページ内をスムーズに移動できるよう、視覚的な導線を設計することも重要です。色、大きさ、配置などを工夫することで、自然な流れで重要な情報やアクションボタンに誘導することができます。
特に、問い合わせフォームや資料請求ボタンなど、ビジネスの成果に直結するアクションへの導線は、特に丁寧に設計する必要があります。これらのボタンが見つけにくかったり、アクセスしにくかったりすると、せっかく興味を持った訪問者を逃してしまうことになります。
継続的な改善の重要性
優れたデザインと構成は、一度作って終わりではありません。実際にホームページを公開した後、アクセス解析データや利用者の反応を見ながら、継続的に改善していくことが重要です。
どのページがよく見られているか、どこで訪問者が離脱しているか、どのボタンがクリックされているかなどのデータを分析し、より効果的なデザインと構成に改善していくことで、ホームページの価値を高めることができます。
次回は、デザインと構成に加えて重要な「ユーザー目線での使いやすさ」について詳しく解説します。どれだけ美しいデザインでも、使いにくければ意味がありません。本当に効果的なホームページを作るための最後のピースについて見ていきましょう。



