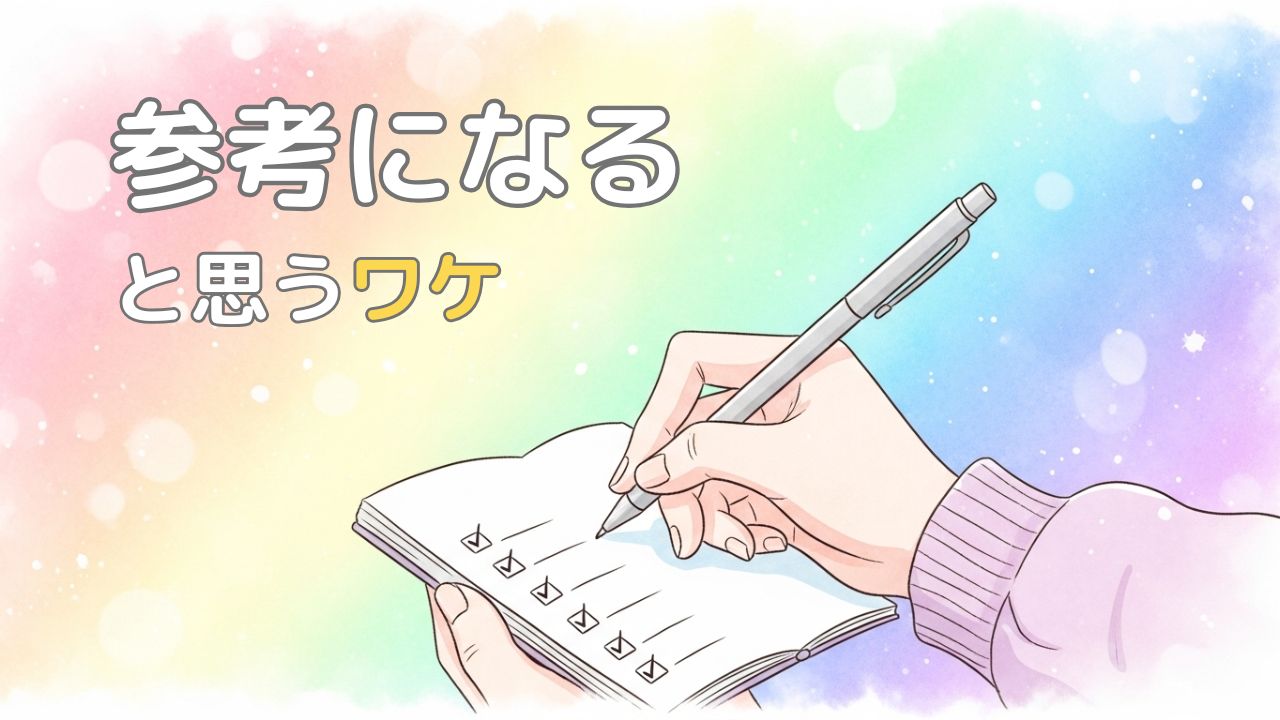第9章:ホームページが不要なケースとは? (1)SNSやポータルサイトで十分な業種・業態
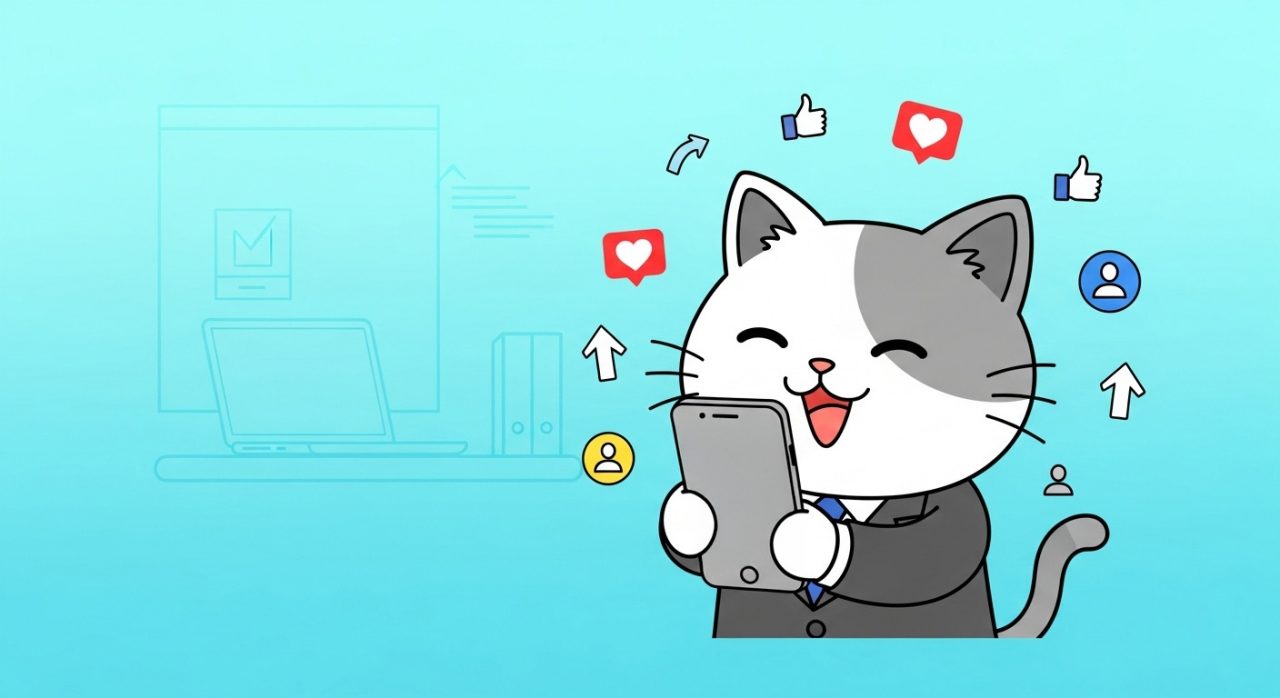
これまで8章にわたって、ホームページの重要性や効果的な運用方法について解説してきました。しかし、もちろんすべてのビジネスにホームページが必要というわけではありません。むしろ、無理にホームページを作るよりも、SNSやポータルサイトに注力した方が効果的な場合もあります。
「ホームページは必要か?」というこのシリーズの根本的な問いに対して、今回は別の視点からアプローチします。どのような業種・業態であれば、ホームページなしでも十分にビジネスを展開できるのか。その判断基準と具体例について詳しく見ていきましょう。
SNSが主戦場となる業種・業態
ビジュアル重視のビジネス
美容・ファッション関連 美容院、ネイルサロン、アパレルショップなど、ビジュアルの魅力が購買意欲に直結する業種では、InstagramなどのSNSが非常に強力なツールとなります。写真や動画で直感的に魅力を伝えられるSNSは、ホームページよりも効果的な集客ツールになることが多いのが現実です。
特に個人経営や小規模店舗の場合、Instagram一つで十分な集客ができているケースも珍しくありません。新しいヘアスタイルやネイルデザインを日々投稿し、フォロワーとのコミュニケーションを通じて予約につなげる。このサイクルが確立できていれば、わざわざホームページを作る必要性は低いかもしれません。
飲食店(特に個人店) 料理の写真が美味しそうに見えるかどうかが来店のきっかけになる飲食店でも、SNSの活用が効果的です。日替わりメニュー、季節限定メニュー、お店の雰囲気などを日々発信することで、「今日はあのお店に行ってみよう」という即座の行動につながります。
また、食べログ、ぐるなび、Googleマップなどのグルメポータルサイトに登録していれば、基本的な情報(営業時間、場所、メニュー、価格帯など)は十分に伝えることができます。
リアルタイム性が重要なビジネス
イベント・ライブ関連 音楽ライブ、イベント企画、ポップアップショップなど、情報のリアルタイム性が重要なビジネスでは、SNSの即時性が大きな武器になります。「明日開催」「本日限定」といった情報は、SNSで発信することで迅速に拡散され、即座の集客につながります。
ホームページでも同様の情報発信は可能ですが、更新の手間やフォロワーへの通知機能などを考えると、SNSの方が圧倒的に効率的です。
若年層がターゲットのビジネス
10代〜20代向けの商品・サービス 若年層をメインターゲットとする場合、彼らの情報収集手段はSNSが中心です。特にInstagram、TikTok、Twitterなどが主要な情報源となっており、ホームページを見る習慣がない層も多く存在します。
このような場合、ターゲット層が実際に使っているプラットフォームで情報発信を行う方が、はるかに効率的な集客が可能です。
ポータルサイトで完結できる業種
専門ポータルサイトが充実している業種
不動産業 SUUMO、HOME’S、athomeなどの不動産ポータルサイトは非常に充実しており、物件探しをする人のほとんどがこれらのサイトから始めます。中小の不動産会社の場合、これらのポータルサイトに物件情報を掲載し、問い合わせ対応を行うことで、十分にビジネスが成立するケースも多くあります。
自社ホームページを持つ場合でも、結局はポータルサイトへの誘導や、ポータルサイトに掲載している情報の二重管理になることが多く、費用対効果を考えるとポータルサイトへの注力だけで十分という判断もあり得ます。
人材派遣・求人関連 Indeed、リクナビ、マイナビなどの求人ポータルサイトが非常に充実している現在、求職者の多くはまずこれらのサイトで仕事を探します。特に中小の人材派遣会社では、ポータルサイトへの求人掲載と適切な対応があれば、自社ホームページがなくても事業運営が可能です。
宿泊施設(小規模) 楽天トラベル、じゃらん、Airbnbなどの宿泊予約サイトが充実している現在、特に小規模な宿泊施設では、これらのプラットフォームだけで十分な予約獲得が可能です。予約システムの構築やクレジットカード決済の導入など、自社で対応するには負担が大きい機能も、ポータルサイトを利用することで簡単に実現できます。
ポータルサイトを活用するメリット
集客力の恩恵 大手ポータルサイトは膨大な広告費をかけて集客を行っており、その集客力の恩恵を受けられることは大きなメリットです。自社で同等の集客力を実現しようとすれば、莫大なコストがかかります。
信頼性の担保 知名度のあるポータルサイトに掲載されていることで、利用者に一定の信頼感を与えることができます。聞いたことのない会社の自社ホームページよりも、有名ポータルサイトの情報の方が信頼されやすい面があります。
機能の充実 予約システム、決済機能、レビュー機能など、自社で構築するには高コストな機能が、ポータルサイトでは標準的に提供されています。
地域密着型の小規模ビジネス
口コミと紹介が中心のビジネス
地域の個人サービス業 地域の小さな修理店、クリーニング店、個人タクシーなど、顧客の多くが近隣住民であり、口コミや紹介が主な集客手段となっているビジネスでは、ホームページの優先順位は低くなります。
Googleマップに正確な情報を登録し、必要最低限の情報(営業時間、電話番号、サービス内容)が検索で見つかる状態にしておけば、わざわざホームページを作る必要性は低いかもしれません。
既存顧客中心のビジネスモデル
リピーター中心の事業 新規顧客の獲得よりも、既存顧客との長期的な関係維持が中心となるビジネスでは、ホームページの重要性は相対的に低くなります。定期的な訪問や電話、場合によってはLINEなどのメッセージツールでのコミュニケーションがあれば、ビジネスは十分に回ります。
ホームページが不要と判断できる条件
以下の条件が複数当てはまる場合、ホームページは必須ではないかもしれません。
ビジネス特性の条件
- ターゲット層がSNSを主要な情報源としている
- ビジュアルでの訴求力が最も重要
- リアルタイムな情報発信が集客の鍵となる
- 充実したポータルサイトが存在し、そこに登録している
運用面の条件
- ホームページ制作・運用のリソースが限られている
- SNSやポータルサイトでの情報発信が既に軌道に乗っている
- 新規顧客獲得よりも既存顧客維持が重要
コスト面の条件
- ホームページ制作・運用費用を他の投資に回した方が効果的
- SNS広告やポータルサイトへの投資で十分な成果が出ている
それでもホームページがあった方が良い場合
ただし、「今すぐは必要ない」と「将来的にも不要」は別の話です。ビジネスが成長し、規模が拡大していく過程で、ホームページの必要性が高まることもあります。
また、SNSやポータルサイトは、プラットフォーム側のルール変更やサービス終了のリスクがあることも忘れてはいけません。自社でコントロールできるホームページを持つことは、長期的なリスク管理の観点からも価値があります。
次回は、期間限定のプロジェクトやイベントサイトにおける判断基準について解説します。永続的な運用を前提としない場合、ホームページの作り方や考え方はどう変わるのかを見ていきましょう。