今騒がれている「ステマ」問題とは?あなたの会社も知らないうちにやってるかも
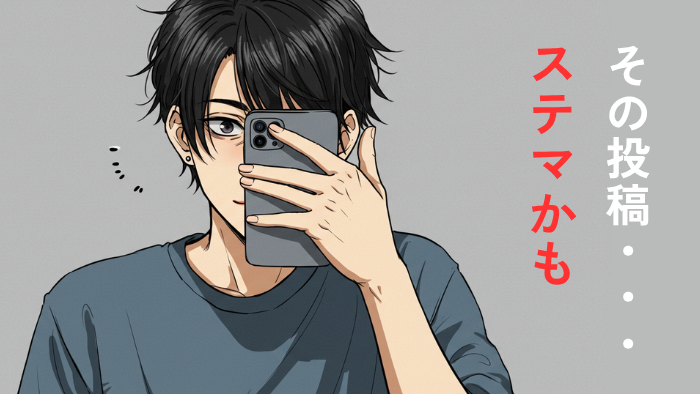
「石破さんを説得できたのスゴい」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」…これ、実は政治家の陣営が用意した「やらせコメント」だったというニュースが大きく取り上げられていましたね。
この小泉進次郎陣営のステマ問題。以前から芸能人やインフルエンサーなどでも問題となり、ステマという言葉を聞いたことがある人がいるかと思います。
これは軽く考えがちなのですが、実は法律違反にも関わってくる大きな出来事なのです。
しかも私達企業でもあり得ることなので、しっかりとお伝えしたいと思います。
小泉進次郎陣営の何がまずかったのか?
今回の問題を整理してみると、小泉陣営がやっていたのは典型的なステマの手法でした。ニコニコ動画という一般ユーザーが多いプラットフォームで、支援者に対して「ポジティブなコメントを書いて欲しい」と依頼し、具体的なコメント例を24パターンも用意していたのです。
法的に問題なのは、これが「広告や宣伝活動であることを隠している」点です。視聴者は一般の人が自然に応援コメントを書いていると思ってしまいますよね。でも実際は、陣営が組織的に指示した「やらせ」だった。これこそがステマの本質的な問題なんです。
2023年10月から、日本では消費者庁がステマを景品表示法違反として厳しく取り締まるようになりました。政治活動でも、もし「事業者」として認定されれば、措置命令や課徴金の対象になる可能性があります。何より、発覚した時の社会的制裁は計り知れません。
「軽く考えがち」だけど、実は違反になることって多い
ステマの怖いところは、多くの人が「これぐらい大丈夫でしょ?」と軽く考えてしまうことです。でも実際には、知らないうちに法律に抵触している可能性が高いんです。
例えば、社員にお願いして自社商品をSNSで投稿してもらう時。「#PR」や「社員の○○です」という表記をつけずに、まるで一般のお客様が投稿しているかのように見せかけたら、それは立派なステマです。友人や知人にお客様の声を書いてもらったり、口コミサイトにレビューを投稿してもらったりするのも同じです。
※自社のサイトやSNSで自社商品やサービスを紹介するのはまったく問題ありません。
インフルエンサーとのコラボも要注意です。「PR」の表記が小さすぎたり、分かりにくい場所にあったりすると、フォロワーは広告だと気づかずに商品を購入してしまうかもしれません。これも消費者庁の規制対象になります。
どんなことが違反で、どこからがグレーなのか?
ステマの境界線は、実は意外とシンプルです。「広告主からの依頼や対価があるのに、それを隠している」場合が法的に問題になります。
明らかに違反になるケース 企業から報酬をもらってSNSで商品を紹介しているのに「#PR」をつけない。これは完全にアウトです。友人に頼んで口コミサイトに良いレビューを書いてもらい、その対価として食事代を払ったりプレゼントを渡したりするのも同様です。
グレーゾーンになりやすいケース 例えば、私たちのようなウェブ制作会社が、会社ブログの「飲食日記」でクライアントのお店を紹介する場合。報酬はもらっていないし、お店から依頼されたわけでもない。でも、読者から見ると「制作会社がクライアントを宣伝している」ように見える可能性があります。
法的には問題ないけれど、後から「実はクライアントでした」と分かると、読者は「隠していた」と感じるかもしれません。こういうケースが「グレーゾーン」と呼ばれる部分です。
透明性が信頼を生む
グレーゾーンを避ける一番の方法は、透明性を保つことです。関係性があるなら、それを隠さずに伝える。これだけで、法的リスクもイメージリスクも大幅に減らすことができます。
さっきの飲食日記の例なら、「実はこのお店、当社がサイト制作でお手伝いしているクライアントさんですが、仕事抜きで食事に行ったら本当に美味しくて」と一言添えるだけで印象が変わります。むしろ「仕事を抜きにしても良かった」という信頼感を持ってもらえるかもしれません。
SNSでも同じです。「#PR」や「#広告」をつけることで効果が下がると心配する方もいますが、実際にはそれほど影響はありません。むしろ正直にやっている企業の方が、長期的には信頼され続けています。
社内ルールを作っておくことの大切さ
ステマを防ぐためには、社内でのルール作りが重要です。特に複数のスタッフがSNSを使っている会社では、誰かが知らないうちに問題のある投稿をしてしまう可能性があります。
「インフルエンサーとコラボする時は必ず『#PR』をつけてもらう」「社員が自社商品について投稿する時は『社員の○○です』と明記する」「お客様の声を掲載する時は、本当のお客様からきちんと許可をもらう」。こうした基本的なルールを決めておくだけで、リスクは大幅に減らせます。
正直なマーケティングが一番強い理由
今回の政界のステマ問題を見ていて改めて思ったのは、結局のところ「正直なマーケティング」が一番強いということです。
短期的には効果があるように見えても、ステマは必ずいつかバレます。そして一度バレると、失う信頼の方がはるかに大きい。逆に、最初から正直にやっていれば、お客様との本当の信頼関係を築くことができます。
「これは広告です」と堂々と言っても、内容が良ければお客様はちゃんと見てくれます。むしろ「この会社は正直だな」と思ってもらえることの方が、長期的にはずっと価値があるんです。
今の時代、消費者の目も肥えています。巧妙に隠そうとすればするほど、かえって不自然さが際立ってしまいます。それなら最初から透明性を保って、商品やサービスの本当の良さで勝負した方が、働いている私たち自身も誇りを持てますよね(^^)



