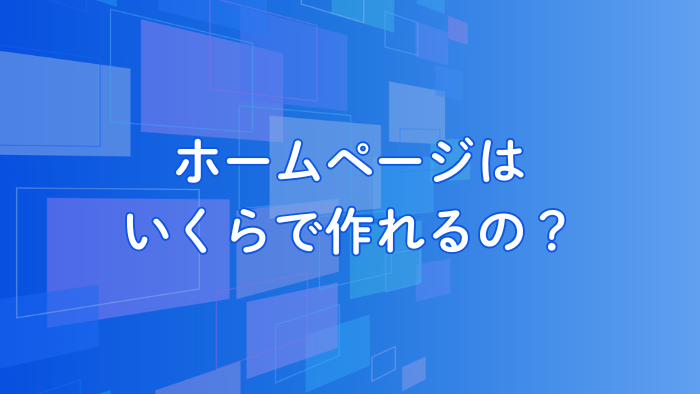西松屋の「ガラガラ戦略」から学んだ、小さな会社でも使える”常識を疑う”ビジネスのヒント

お子さんがいる家庭では一度は行ったことはある西松屋。3人の子どもがいる私ももちろん行ったことはあります。
西松屋のイメージでこんな感じですよね。
- 安い
- 商品はなんだか安心できる
- 店内ゆったり…というかガラガラ
そう、西松屋って店内はガラガラなんです。おかげで広い通路をベビーカーを押しながらゆっくりと見て回ることができますよね。
一般的に考えると、店がガラガラというのは経営上良くないサインのはず。でも西松屋は全国にたくさん店舗があって、明らかに繁盛している。
実際に業績好調で売上高はなんと30期連続で過去最高を更新しており、営業利益率も競合他社を圧倒する高さらしいです。
この「違和感」の正体が分からずにいたところ、たまたまネットで西松屋の経営戦略についての記事を見つけました。読んでみると「なるほど!」と膝を打つような内容で、小さな会社を経営している私たちにも参考になることがたくさんありました。
「ガラガラ」は偶然ではなく戦略だった
記事によると、西松屋は意図的に店舗を「ガラガラ」の状態に保っているとのこと。売上が一定基準を超えると近隣に新店舗を出店して、あえて分散させているそうです。
なぜそんなことをするのか?答えは顧客体験にありました。
西松屋の主な顧客は親子連れ。ベビーカーを押したり、小さな子どもの手を引いたりしながら買い物をする人たちです。そんな顧客にとって
- いつ行っても空いていて他の客を気にしなくていい
- 通路が広くてベビーカーで移動しやすい
- 店員が少なくて気兼ねなく買い物できる
- 静かで子どもが寝ていても安心
こういった環境こそが本当に求められていた「価値」だったんですね。
常識を疑うことから始まる差別化
この西松屋の戦略を知って、改めて感じたのは「業界の常識を疑うことの大切さ」です。
小売業界では一般的に「店舗は賑わっている方が良い」「店員は手厚く接客するべき」「BGMで活気を演出するべき」といった常識があります。でも西松屋は、これらの常識をあえて無視しました。
その結果、30期連続増収という驚異的な成果を上げています。営業利益率も競合の赤ちゃん本舗が1.5%に対して西松屋は6.7%と、圧倒的な差をつけています。
長崎の小さな会社でも応用できるヒント
この西松屋の事例、実は私たちのような地方の小さな会社でも応用できる要素がたくさんあると思います。
お客様が本当に求めているものを見極める
例えば、カフェを経営していて「お客様は豪華な内装を求めている」と思い込んでいませんか?実際には「落ち着いて過ごせる空間」や「ゆっくり話ができる場」や逆に「にぎわいのある楽しげな場所」という場合も場所やカフェのコンセプトによって変わってきますよね。
もちろん西松屋のような物販の会社と小さなカフェを普通に比べてはいけません。小さなカフェが常にガラガラしていては売り上げが立ちませんからね。
お客さまが何を求めているのか。そして自分の会社は何で利益をいただくのか。これをしっかり照らし合わせないといけません。
手厚いサービスが正解でない場合もある
長崎は人情味溢れる土地柄なので、ついつい「お客様には手厚くサービスを」と考えがちです。もちろんそれも大切ですが、時にはお客様が「そっとしておいて欲しい」と思っている場合もあります。
地元のあるカフェは、あえて「注文を取りに行かない」スタイルを貫いています。お客様がカウンターに注文しに来るセルフ形式なのですが、これが「気兼ねなく長居できる」と評判になってるケースもあります。
コストを徹底的に見直す
西松屋の成功要因の一つが、販管費の徹底的な圧縮です。1店舗あたりの従業員数は約4人、全社員数695人に対して店舗数は1145店舗と、驚くほど効率的な運営をしています。
小さなお店でも改めて考えてみると、「これって本当に必要?」と疑問に思う業務や費用がいくつかあるのではないでしょうか。例えば、毎日の清掃を外注していたけれど、開店前の時間を活用して自分たちでやることでコストを削減したり、逆に清掃を外注することで自分達のすべきことに集中できることも。また、必要以上に豪華な包装材を使っていたのを見直したり。
地方だからこそできる「ガラガラ戦略」
考えてみると、地方には「ガラガラ戦略」を実践しやすい環境が整っているかもしれません。
都市部では賃料の関係で狭い店舗しか借りられなくても、地方なら広いスペースを確保しやすい。人件費も抑えやすいし、地域密着型のサービスなら過度な接客よりも「親しみやすさ」の方が重要視されることも多いです。
長崎の企業も、都市部の常識にとらわれず、地方ならではの戦略を考えてみる価値があるのではないでしょうか。
常識を疑う勇気を持つこと
西松屋の事例を知って改めて感じたのは、「常識を疑う勇気」の大切さです。
「こうするべき」「これが普通」という思い込みを一度脇に置いて、「お客様が本当に求めているものは何か?」「もっと効率的なやり方はないか?」と考えてみる。
簡単そうに見えて、実はとても勇気のいることです。でも、その一歩が大きな差別化につながる可能性があります。
まとめ:小さな会社だからこそできること
西松屋のような大企業の戦略を、そのまま小さな会社に当てはめることはできません。でも、「常識を疑う」「お客様の本当のニーズを見極める」「戦略的に何かを捨てる」といった考え方は、規模に関係なく応用できると思います。
むしろ、小さな会社の方が意思決定が早くて、思い切った戦略転換がしやすいかもしれません。
長崎の小さな会社だからこそできる、独自の「ガラガラ戦略」を見つけてみませんか?きっと思わぬ突破口が見つかるはずです(^^)