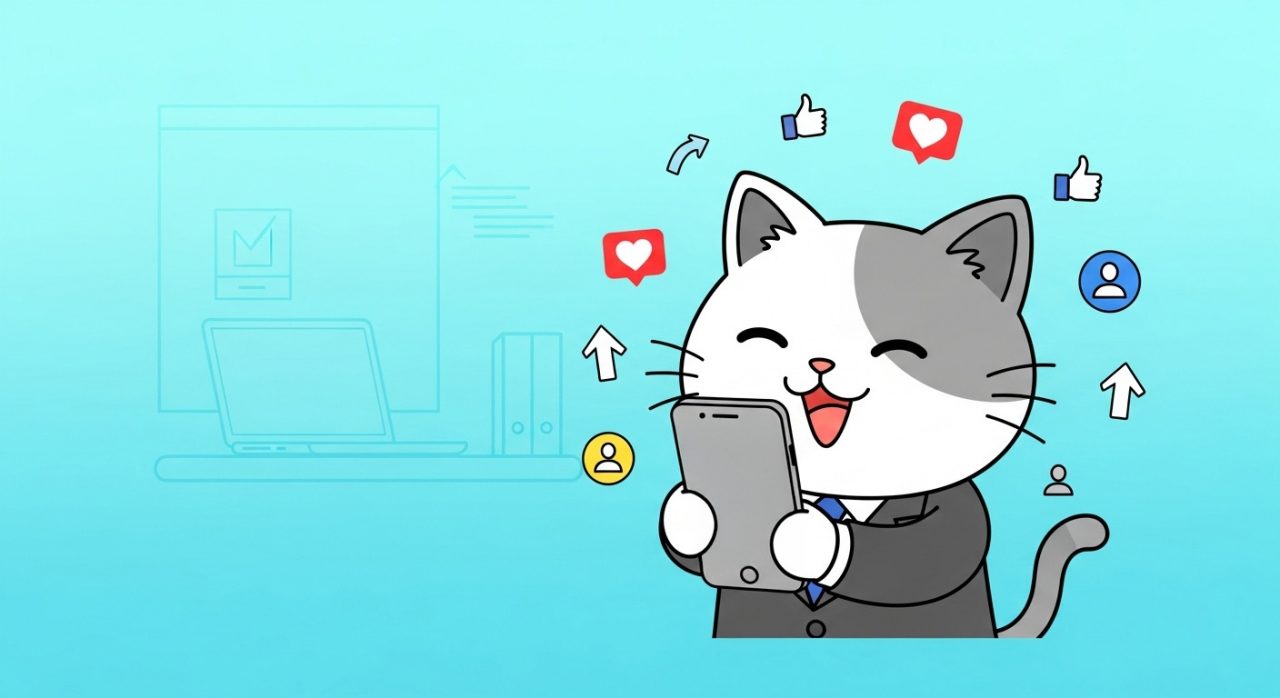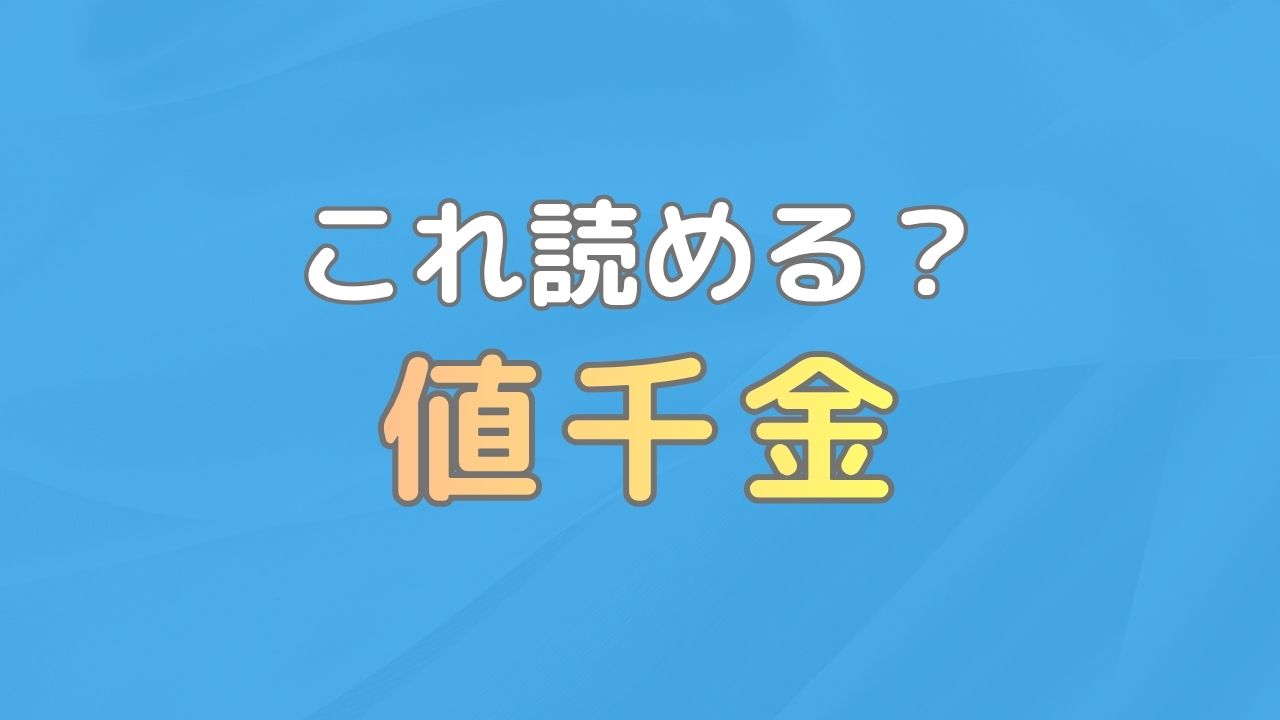なぜ人は「参考になる」と感じるのか
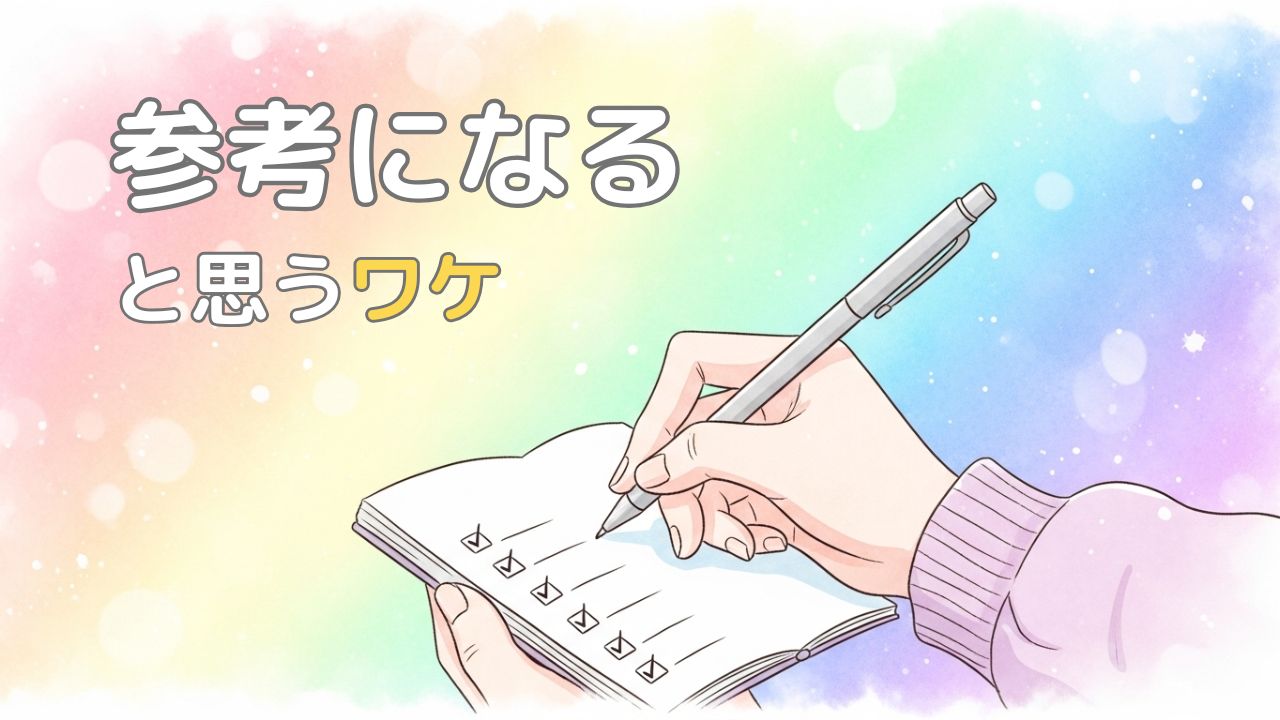
「これ、保存しておこう」
SNSを見ていて、思わず保存ボタンを押す瞬間があります。後で見返したい、実際に使いたい、誰かに教えたい…。
でも、同じようなテーマの投稿でも、保存されるものとスルーされるものがあります。
その違いは何でしょうか? 今日は「参考になる」の核心、それは「明日から使える具体性」について深く掘り下げます。
「いい話だった」で終わる投稿
あるマーケティングの専門家が、こんな投稿をしました。
「SNS運用で大切なのは、継続性です。毎日コツコツ投稿することが、フォロワーを増やす近道です。諦めずに続けましょう!」
「いいね」は100ほどついたものの、保存は5件。コメントもほとんどありませんでした。
一方、同じ人が別の日にした投稿:
「SNS投稿、ネタ切れしますよね。私は毎週日曜日の夜、スマホのメモに『今週あった小さな出来事』を5つ書き出します。お客様との会話、失敗談、気づいたこと…なんでもOK。それを見ながら、月曜から金曜の投稿を作ります。30分で1週間分のネタができます」
この投稿は、保存が350件。「やってみます!」というコメントが50件以上つきました。
何が違ったのか?
前者は「正論」です。確かに継続は大切。でも、「どうやって?」が分かりません。
後者は「方法」です。日曜の夜に、メモに、5つ書き出す。30分で1週間分。すべてが具体的です。
「参考になる」とは、「明日、自分にもできそう」と思えることなんです。
具体性の3つのレベル
「具体的に書く」と言っても、レベルがあります。
レベル1「何をするか」だけ
「ホームページは定期的に更新しましょう」
これでは、まだ足りません。いつ? どのくらいの頻度で? 何を更新するの?
レベル2「いつ、何を、どのくらい」
「ホームページは月に1回、お知らせ欄を更新しましょう」
少し具体的になりました。でも、まだ「何を書けばいいの?」が分かりません。
レベル3「いつ、何を、どのくらい、どうやって」
「ホームページは月末の金曜日、お知らせ欄に『今月の実績』を3つ書きましょう。完成したプロジェクト、お客様からの感想、社内の出来事…何でもOK。各100文字程度で十分です。スマホから5分で更新できます」
ここまで具体的だと、「あ、それならできそう」と思えます。
ビジネスにおける「具体性」の威力
具体性は、ビジネスの成果を大きく変えます。
例1:あるWeb制作会社の提案書
以前、私はこんな提案をしていました。
「ホームページをリニューアルすることで、集客力が向上します。デザインを刷新し、SEO対策を施し、使いやすさを改善します」
これでは、お客様は「で、具体的に何が変わるの?」と思うだけです。
今はこう提案します。
「現在のホームページは、お問い合わせフォームまで5クリック必要です。これを2クリックに減らします。また、スマホで見た時に文字が小さくて読みにくい箇所が3カ所あります。これを修正します。さらに、Googleで『長崎 ホームページ制作』と検索した時に、現在15位ですが、これを3ヶ月で5位以内に上げます。その結果、月間の問い合わせ数を現在の3件から10件に増やすことを目指します」
後者の方が、成約率がなりそうですよね。お客様が「何が、どう変わるのか」を具体的にイメージできるからです。
例2:ある飲食店のSNS投稿
投稿A 「当店では新鮮な食材を使っています。ぜひお越しください!」
投稿B 「今朝5時、長崎港で水揚げされた鯵を仕入れてきました。12時のランチタイムまであと2時間。今、店主が下処理をしています。鯵フライ定食、本日限定20食です」
投稿Bは、来店客数が増えそうですよね。「今日の12時に行けば、朝獲れた鯵が食べられる」という具体的なイメージが湧くからです。
事例3:あるコンサルタントのアドバイス
クライアント:「売上を上げたいんです」
コンサルタントA 「まずは顧客満足度を高めることが重要です。お客様の声に耳を傾け、サービスを改善していきましょう」
これでは、クライアントは「で、明日何をすればいいの?」となります。
コンサルタントB 「明日から、お会計の時に『本日はいかがでしたか?』と一言添えてください。お客様が何か言ってくれたら、スマホのメモに記録します。1週間で20人分集まったら、一緒に見直しましょう。そこから改善点を3つ決めて、来月実行します」
後者は「明日からできること」が明確です。だから、実際に動けるのです。
「具体的に書く」5つのコツ
では、どうすれば具体的に書けるのでしょうか?
1. 数字を入れる
「定期的に」→「週に2回」 「少し時間をかけて」→「15分」 「たくさん」→「10個」
数字があると、「どのくらい」が明確になります。
2. 固有名詞を使う
「ツールを使う」→「Googleカレンダーを使う」 「SNSで発信」→「Instagramのストーリーズで発信」 「資料を作る」→「Canvaでチラシを作る」
具体的なツール名があると、イメージしやすくなります。
3. 手順を示す
「まず〇〇、次に△△、最後に□□」
ステップがあると、「自分にもできそう」と思えます。
4. 時間を指定する
「朝起きたら」→「朝7時、歯を磨いた後」 「週末に」→「日曜日の夜9時、子どもを寝かせた後」
いつやるかが決まると、実行しやすくなります。
5. 失敗例も示す
「最初、私は〇〇をやって失敗しました。だから△△に変えたら、うまくいきました」
失敗例があると、「その道は通らなくていいんだ」と分かります。これも立派な「参考になる情報」です。
「具体的すぎる」は存在しない
「こんなに細かく書いたら、長すぎませんか?」
よく聞かれる質問です。でも、「具体的すぎる」という失敗は、ほぼありません。なぜなら、人は「自分に必要な情報」だけを読むからです。
「あ、これ自分には当てはまらないな」と思ったら、読み飛ばします。 「これ、まさに自分のことだ!」と思ったら、最後まで読みます。
むしろ、抽象的で「結局何をすればいいの?」となる方が問題です。
「参考になる」の先にあるもの
「参考になった!」と思ってもらえると、何が起きるでしょうか?
保存される。シェアされる。実際に試してもらえる。
そして、それがうまくいったら、「この人の言うことは信頼できる」となります。信頼が生まれると、次はあなたの商品やサービスに興味を持ってもらえます。
「この人が勧めるなら、きっと良いものだろう」
そう思ってもらえるのです。
「明日から使える」が最強
「参考になる」の本質は、「明日、自分にもできそう」と思えることです。そのためには、具体的に書く。数字、固有名詞、手順、時間を入れる。抽象的な正論より、具体的な方法。理想論より、実践できる小さな一歩。お客様が、読んだ後に「よし、やってみよう」と思える具体性。それが、「参考になる」を生み出します。