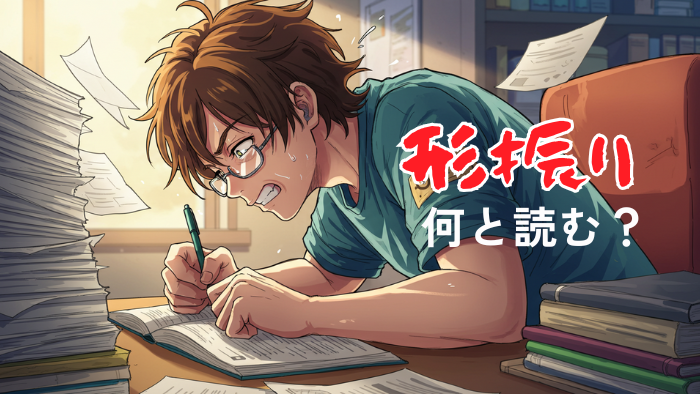長崎くんち(おくんち)を調べてみた~興味がない人でも持つかもしれない3つのポイント~
『興味がないなら 調べてみよう ホトトギス』
これは私が今作った言葉です。
中学生からは長崎で育った私ですが、長崎くんちにあまり興味がありませんでした。
学生の時はお祭りという感覚で出店に行くのはとても好きでしたし、「おくんち」に命をかけている人達を見たこともあるし、大ファンという友人もいます。そんな環境に身を置きながらも、興味は…いまひとつ出ていませんでした。
でも、会社のブログで長崎のことを書く以上、地元の伝統行事を知らないわけにはいかないと思い、改めて調べてみました。「興味がないなら強制的に調べてみよう、長崎くんちのこと」の実施です。
調べてちょっとだけ詳しくなった私が、知らない方々のためにドヤ顔でお伝えします(^^)
調べて驚いた3つのポイント
1. 『7年に1度』しか出番が来ない
7年に1度というフレーズは聞いたことありますが、何がそうなのか詳しく知りませんでした。
長崎くんちで踊りを披露する「踊町(おどりちょう)」が、7年に1度しか出番が回ってこないとのこと。
踊町(おどりちょう)というのは、その年に踊りや出し物を披露する当番の町のことです。長崎市内には全部で58の町があって、それが7つのグループに分かれているらしい。毎年違うグループが担当するので、自分の町に順番が回ってくるのは7年後。つまり、一度やったら次は7年待たないといけないんです。
オリンピックでも4年に一度なのに7年に1度ってすごいですよね。
7年って…子供が小学校に入学したら、次は中学生になってる。結構な時間ですよね。だから、その1回にかける地元の人の情熱が半端じゃないらしいです。1年以上前から準備を始める町もあるとか。
知識が浅い私は「コッコデショ」が7年に1度というイメージでした。
コッコデショは「出し物の種類」の一つでして、正式には「太皷山(たいこやま)」と呼ばれるもの。コッコデショは7年に1度しか見られない演目の一つですが、それを披露するのは特定の町(椛島町など)が担当する年だけです。今年2025年はコッコデショを担当する町が当番じゃないので、コッコデショは見られないということになります。
とにかく街中で見かける踊りや出し物は、7年に1度のチャンスに賭けた地元の人たちの努力の結晶なんですね。見方が変わります。
ちなみに今年2025年は、西古川町、新大工町、諏訪町、榎津町、賑町、新橋町の6つの町が担当だそうです。例年は7つの町が担当するらしいのですが、今年は金屋町が不参加で6町での開催になるとのこと。次にこの6町が揃って見られるのは7年後。今年しか見られない組み合わせなんですね。
2. GPSで追跡できる現代の祭り
「庭先回り」というのがあって、踊町の人たちが街のあちこちで演技を披露するそうです。昔ながらのお祭りなのに、なんとスマホアプリで神輿や踊りの現在地がリアルタイムで分かるんだとか。
「長崎くんちナビ」というアプリがあって、どの踊町がどこにいるかGPSで追跡できる。これ、すごくないですか?
伝統行事なのに最新テクノロジーを使っている。しかも、それが違和感なく受け入れられている。この「古いものと新しいもの」のバランス感覚、長崎らしいなと思いました。
観光客の方も、これがあれば効率よく見て回れますよね。地元の人にとっても便利だし、お祭りを盛り上げる良い工夫だと思います。
3. 起源が意外とドラマチック
長崎くんちは1634年から始まったそうですが、その起源がちょっと意外でした。
最初に踊りを奉納したのは、2人の遊女だったそうです。高尾さんと音羽さんという方が、諏訪神社の前で謡曲「小舞」を奉納したのが始まりとか。
遊女という立場でありながら、神社に踊りを奉納する。それが400年近く続く伝統行事のスタートになった。なんだかドラマがありますよね。
しかも、1634年といえば、長崎では出島が作られたり、眼鏡橋が架けられたりした年。長崎が国際貿易の拠点として栄えていた時代です。だから、くんちの踊りには中国やオランダの影響を受けたものが多いんだそうです。
今年の見どころ
今年2025年は「龍踊(じゃおどり)」が見られる年だそうです。
龍踊は長崎くんちの代表的な演し物で、不老長寿の源である月を食べようとする龍の姿を表現したものらしい。諏訪町という町が担当していて、7年に1度しか見られない演目です。
他にも、川船、阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)、曳壇尻(ひきだんじり)など、今年ならではの演し物があるとのこと。次にこの組み合わせが見られるのは7年後。そう思うと、ちょっと特別な気がしてきますね。
「もってこーい!」の意味
くんちで一番有名な掛け声が「もってこーい!」です。これ、聞いたことある人も多いと思います。
調べてみたら、これは「もう一回やってくれ!」という意味のアンコールなんです。演技が素晴らしかった時に、観客が叫ぶんですね。
7年に1度の晴れ舞台で、観客から「もってこーい!」と言われたら、踊っている人たちはどんなに嬉しいでしょうか。そう思うと、この掛け声の重みが違って聞こえてきます。
おくんちは日本三大祭りの1つ?
学生の頃はこう思っていました。日本三大祭りの1つだなんてすごいやん、と…
しかし実際は「日本三大くんち」の1つです。
- 長崎くんち(長崎県長崎市)
- 博多おくんち(福岡県福岡市)
- 唐津くんち(佐賀県唐津市)
九州に集中していますね。「くんち」は九州北部地方で秋祭りを指す呼び方で、「九日(くにち)」が訛ったものとか、「供日(くにち)」から来ているなど諸説あります。
長崎くんちは特に、異国文化の影響を受けた独特の演目や豪華絢爛さで知られていて、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。三大くんちの中でも特に華やかで規模が大きいと言われていますね。
興味を持って調べると見方が変わる
調べたことで、少し見方が変わりました。
さまざまな背景を知ると、街中で聞こえる「もってこーい!」の声も、違って聞こえてくる気がします。
長崎で仕事をしている以上、地元の伝統行事は大切にしたいものですね。興味がなくても、知ろうとすれば面白いことが見つかる。それが分かっただけでも、今回調べてみて良かったです。
皆さんもおくんちに限らず、興味がなかったことをちょっと調べてみると意外な発見があるかもしれませんよ (^^)

画像生成用のプロンプトを丁寧に書いて、龍踊を再現したもの。うーん、カッコイイ!