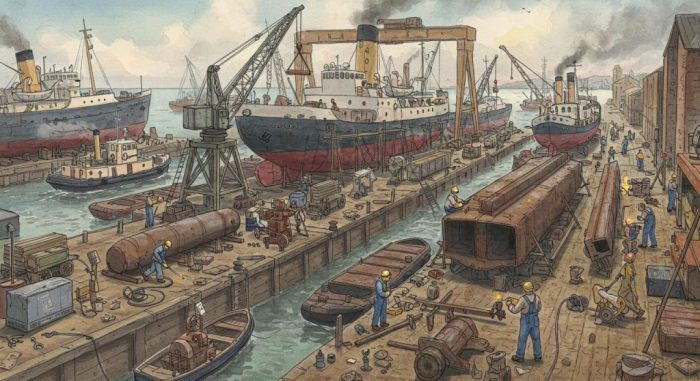ファミマのAI発注システムが話題に~週6時間の業務削減が現実に~

AIが業務効率化に繋がるのは今となっては周知のことですが、実際に具体的に大手企業が本格導入し、明確な効果を示したケースとして、ファミリーマートの取り組みが注目されています。
週6時間の業務時間削減という具体的な数字で効果が示されたのは、コンビニ業界だけでなく、様々な業界にとって参考になる事例だと思います。
どんなシステムなの?
ファミマが7月10日に発表した「AIレコメンド発注」は、おむすびや弁当、サンドイッチなどの発注数をAIが自動で提案してくれるシステムです。
6月末から全国500店舗で運用が始まったそうで、AIが過去1年間の販売実績や店舗周辺の通行量、天気、祝日などのデータを分析して、日別・便別・単品別に最適な販売予測数を算出してくれるんです。
しかも、同じような立地で高い利益を上げている他店舗の販売データを参考に、自店でまだ扱っていない売れ筋商品の提案までしてくれるというから驚きです。
発注作業の大変さ
私も若かりし頃コンビニでバイトをしていたのですが、コンビニの発注作業って、想像以上に大変なんですよね。
私は携わっていませんでしたが店長や社員があくせく頑張っていたのを思い出します。
毎日何百種類もの商品を、売れ行きを予測しながら発注しなければならない。少なすぎると売り切れで機会損失になるし、多すぎると廃棄ロスになってしまう。
天気が悪い日は温かいものが売れるし、暑い日は冷たいものが売れる。イベントがあると人の流れが変わるし、新商品が出ると売れ行きが読めない。
そんな複雑な要因を考慮しながら、毎日発注数を決めるのは、本当に頭を使う作業です。ベテランの店長さんでも、「今日はこれくらいかな」と経験と勘に頼る部分が大きかったと思います。
週6時間削減の意味
「週6時間の削減」と聞くと、一日あたり約50分くらいの計算になります。
これって、発注作業にかかっていた時間がかなり短縮されるということですよね。その分、店員さんは接客や清掃、品出しなど、他の重要な業務に時間を使えるようになります。
人手不足が深刻な小売業界では、これは本当に大きなメリットだと思います。
AIが考慮できない部分は人間がフォロー
面白いのは、AIだけに任せっきりにするのではなく、人間とAIの役割分担をしっかり考えているところです。
新商品や販促商品、イレギュラーなイベントなど、AIが考慮できない要素については、各店舗が状況に合わせて手動で調整するとのこと。
これって、すごく現実的なアプローチだと思います。AIの得意な部分はAIに任せて、人間の判断が必要な部分は人間が担当する。理想的な協働関係ですね。
フードロス対策にも効果
このシステムのもう一つの大きなメリットは、フードロス対策になることです。
適切な発注量を予測することで、過剰な発注を防ぎ、食品廃棄を減らすことができます。環境問題が注目される中、これは企業の社会的責任という観点からも重要な取り組みです。
消費者としても、お弁当やおにぎりが無駄に廃棄されるのは見ていて心が痛いですからね。
他の業界への応用可能性
このファミマの取り組みを見ていると、他の業界でも同じような発想が活かせそうだなと思います。
例えば、レストランの仕入れ管理、アパレル店舗の在庫管理、書店の発注業務など、需要予測が重要な業務はたくさんあります。
もちろん、それぞれの業界特有の要因があるので、そのまま適用するのは難しいでしょうが、「データを活用して予測精度を上げる」という基本的な考え方は応用できそうです。
働き方改革の一環として
最近、どの業界でも働き方改革が叫ばれていますが、単純に労働時間を短くするだけでは、仕事の質が下がってしまう可能性があります。
でも、こういったAI活用による業務効率化なら、仕事の質を保ちながら労働時間を短縮できます。これこそが、本当の意味での働き方改革なのかもしれません。
技術の進歩を実感
正直、「AIが発注を提案してくれる」なんて、少し前までは SF の世界の話のように感じていました。
でも、今やそれが現実になっている。しかも、全国500店舗という大規模で実用化されているのを見ると、技術の進歩の速さを改めて実感します。
今後の展開に注目
ファミマは「売上や店舗収益への効果をふまえ、展開店舗の拡大を目指す」としているので、今後の展開が楽しみです。
効果が確認できれば、全国の店舗に展開されるでしょうし、他のコンビニチェーンも追随してくるかもしれません。
消費者にとってのメリット
私たち消費者にとっても、これはメリットがありそうです。
適切な発注により、欲しい商品が品切れしている確率が減るでしょうし、店員さんが他の業務に時間を使えることで、店舗全体のサービス品質向上につながるかもしれません。
まとめ
ファミマのAI発注システムは、単なる技術革新を超えて、働き方改革、環境問題、サービス品質向上など、様々な社会課題の解決につながる可能性を秘めています。
週6時間という具体的な数字で効果が示されているのも説得力がありますし、人間とAIの適切な役割分担も参考になります。
これからも、こういった「人間とAIが協働する」事例が増えていくんでしょうね。技術の進歩によって、私たちの生活がより便利で快適になっていくのを見るのは、やっぱり楽しいものです。
次回コンビニに行くときは、「このお弁当の発注、AIが提案したのかな」なんて考えながら商品を選んでみようと思います (^^)