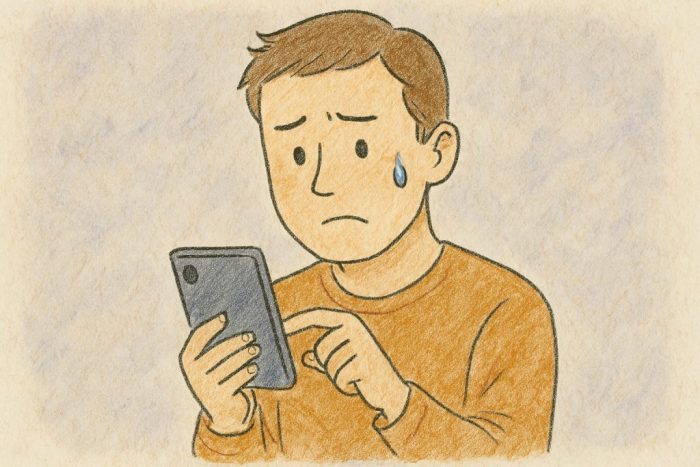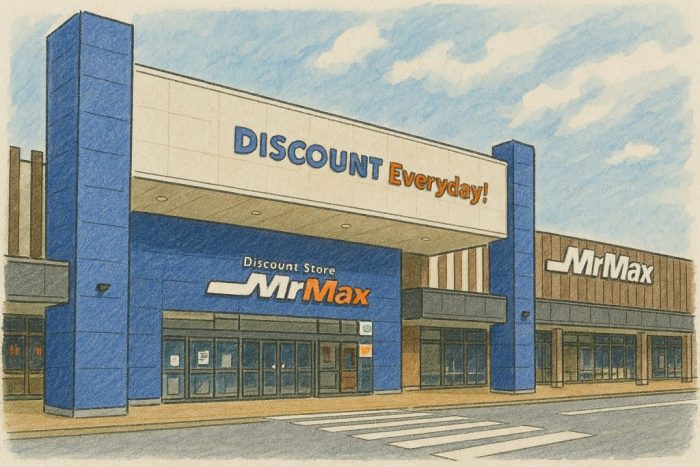SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺って?— 被害総額2億円超、誰にでも起こり得る話
先日、長崎県警から発表された衝撃的な数字。
SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺の被害額が、今年3月までに2億円を超えたというニュースが報じられました。
長崎県内だけで32件、被害総額は約2億2815万円。
さらに、いわゆる「ニセ電話詐欺(オレオレ詐欺など)」でも1億2000万円以上の被害が発生しています。
ニュースを見た瞬間、「こんなに!?」と驚くと同時に、どこかで「私は大丈夫」と思ってしまう自分もいたのですが、実際に手口を見てみると、それがいかに危うい感覚かがよく分かります。
SNS型詐欺とは?— 身近すぎる危険
最近増えているのが「SNS型投資詐欺」と「ロマンス詐欺」。
言葉の通り、SNS上で関係性を築いていく中で、信頼させ、お金を騙し取るという手口です。
たとえば…
【SNS型投資詐欺のパターン】
- インスタやLINEで「FXで稼いでいる」「仮想通貨で資産形成している」という投稿
- その投稿主からDMが届く
- 「少額から始められる」「今がチャンス」などと勧誘され、専用サイトやアプリに誘導
- 最初は利益が出ているように見せかけて出金もできる
- 徐々に大金をつぎ込ませ、最終的には出金できず連絡も途絶える
【ロマンス詐欺のパターン】
- SNSやマッチングアプリで知り合う
- 外国人や海外駐在員を名乗る(写真も美男美女)
- 恋愛関係を演出して信頼を得る
- 「困っている」「ビジネスに投資してほしい」「送金が止まっている」と金銭の要求が始まる
- 渡したお金は戻らず、連絡もつかなくなる
「引っかかりやすいタイプ」とは?
こう聞くと「私は大丈夫」と思うかもしれませんが、引っかかる人は決して騙されやすい人ではなく、“優しい人”や“まじめな人”が多いのが特徴だと言われています。
- 真面目に資産形成を考えている
- 恋愛に対して真剣である
- 相手を信じようとする
- 「損をしたくない」という気持ちが強い
- 家族や周囲に相談しにくい(または一人で抱え込む)
こういった“まっすぐな気持ち”を逆手にとってくるのが、詐欺の怖いところなんです。
もしものための「対応策」
じゃあ、どうやって自分を守ればいいのか?
ポイントは「自分だけで判断しない」ということです。
- うまい話が来たらまず冷静に、すぐには返事をしない
- 家族や信頼できる友人に相談する
- 金融商品や投資アプリについては公式情報や金融庁のリストで調べる
- SNSやマッチングアプリで知り合った人に「お金の話」が出てきたら100%警戒する
- 「今すぐ」「チャンスを逃すな」などの煽り文句は危険信号
特に、「自分は大丈夫」と思っている人ほど、逆に詐欺師の“標的”になりやすいとも言われています。気をつけていても、疲れていたり、精神的に落ち込んでいたりするタイミングで判断力が鈍ることも。
被害者を「騙される側」と決めつけないで
詐欺の被害に遭った人を「なんでそんなのに引っかかるの?」と責めてしまう風潮もありますが、これは本当に危険です。
詐欺は、冷静に考えられなくなるように仕組まれているもの。
むしろ、「こういう話、最近多いらしいよ」「気をつけてね」と、周囲がさりげなく声をかけられる環境を作ることが、被害を防ぐ一歩になります。
万が一、不安に思ったら…相談できる窓口はこちら
「もしかして、これって詐欺かも?」
「でも誰に聞けばいいか分からない…」
そんな時のために、各種相談窓口があります。
一人で抱え込まず、まずは誰かに相談してみてくださいね。
■ 消費者ホットライン(局番なし 188)
お住まいの地域の消費生活センターに繋がります。
「少しでも不安がある」「なんとなく怪しい」そんな時にも気軽に相談できます。(通話料がかかります)
※携帯からもかかります
※土日も対応しているセンターもあります
■ 長崎県警「詐欺・悪質商法 相談窓口」
電話:095-820-0110(長崎県警察本部)
警察は被害を未然に防ぐための相談も受け付けています。
「被害ではないけど相談だけしたい」でも問題ありません。
小さな違和感が、被害を防ぐ
「怪しい」と思った時点で、それは“あなたのセンサー”がしっかり働いている証拠。
気になる話は、まず一呼吸おいて、誰かに話してみる。
たったそれだけでも、被害を大きく防げることがたくさんあります。
身近な誰かにも、この情報が届きますように。
そして、安心してインターネットやSNSを楽しめる社会でありますように…