これは何と読む?『塩梅』
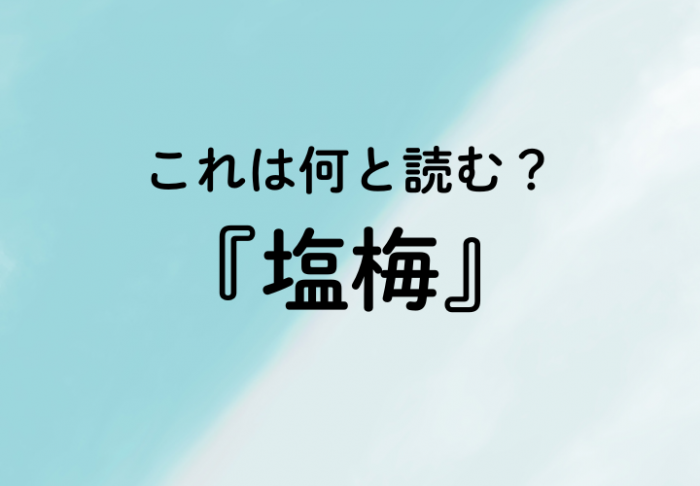
これは僕の好きな言葉です。
『塩梅』
どうでしょう、この言葉は知っている人が多い気はするのですがそれはあくまでも私のイメージ。知らなくても決して恥ずかしいことではありませんし、今回で知れば良いのです!
さて、読み方は「しおうめ」で正解でもいいんですけどね、正解は
あんばい
です。
塩梅(あんばい)とは
大きく2つの意味があります。
1. 味加減・調味の具合
料理において、「塩」と「梅(酸味)」のバランスを指すことから発展し、
「味付けの加減」や「ちょうど良い味の具合」 という意味で使われます。
「このスープ、塩梅がいいね」
→ 塩加減や味付けがちょうど良い
2. 物事の具合・状態・様子
転じて、料理だけでなく物事全般の調子や具合、バランスの良し悪しを表すときにも使われます。
「体の調子」や「仕事・計画の進み具合」など、幅広く使える言葉です。
「体の塩梅が悪い」
→ 体調が良くない
「仕事の塩梅を見て出発する」
→ 仕事の進み具合や様子を見て判断する
僕は2の方をよく使うのですが、「良い塩梅(あんばい)で」って言うと、ちょうどいい感じに整っているニュアンスが出ます。
塩梅(あんばい)の起源
「塩梅(あんばい)」という言葉の起源は、中国の調味料に関する考え方に由来しています。
もともと「塩梅」は、文字通り「塩」と「梅」を指す言葉でした。
塩(しお) … 料理の味を調える基本的な調味料
梅(うめ) … 酸味を加えるために使われるもの
この二つをうまく組み合わせることで、料理の味のバランスを取るという考え方がありました。特に中国では、料理の味付けにおいて 塩と酸味(酢や梅) のバランスが重要視されていたため、「塩梅」が 味の加減を整えること を意味するようになりました。
やがてこの意味が転じて、物事の具合や調子を整えることという広い意味を持つようになり、日本でも「塩梅」が 状況の調整 や 健康状態 などを指すようになったのです。
つまり、もともとは料理の味付けの話だったのが、転じて「ちょうど良い加減」や「物事のバランス」という意味で使われるようになったんですね。
塩梅のちょうど良さ
世の中には白か黒では表現できないようなことがたくさんあります。ここは白7割、黒3割…のようにそれぞれのバランスをなんとなく合わせないといけないこともしばしば。これでもまだはっきりしている方で数字では表せられないぐらいにあいまいな時もたくさんあります。
そんな時にこの塩梅の表現をとても使いやすいですよね。
しかも塩梅って決して適当に決めているのではなくて、度合いを見ながら微調整している感じがでます。
でもはっきり決めるのが難しいものごとに使えるので便利な言葉なんです。
きっちり決めることだけが正解じゃない。
その時その場の“良い塩梅”を探りながら、生きていけたらちょうどいいのかもしれませんね(^^)



